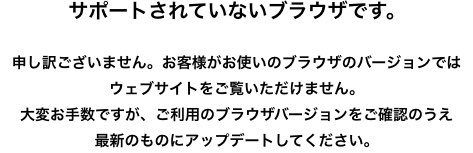ブログ
公開:2025.07.16 07:07 | 更新: 2025.07.16 10:07
日本のコース管理の自動化はだいぶ遅れてるよね、という話

10年ぐらい前にGPSを使った肥料の自動散布が話題になったことがあったんですが、それ以来日本では自動化の話はあまり話題になってませんでした。日本だとバロネスがフェアウェイを自動で刈れるモアを売り出していますが、重い、遅いなど正直あまり評判が良くなく、ルンバのようなロボットタイプの自動刈り込み機もワイヤーで境界を設定しないといけないなど実用性が乏しいとのことで、あまり関心が高まらなかったように思います。
それでも部分的にロボットモアを導入するコースも増えてきていて、さすがに最新の情報を仕入れようと2月にサンディエゴの展示会GCSAAに行ってきました。ロボットモアではハスクバーナが代表的なメーカーで、日本ではやまびこがエコーという商品を出しています。日本では販売されていないですがクレス(Kress)というオランダの会社の商品も有力なメーカーだそうです。
自動化にはこれまでの大型機械を自動で動かす方向性とロボットタイプの小型モアという方向性の二つがあります。特殊なケースとして人間が乗ることを想定しない大型のフェアウェイモアのFireFlyという商品も発売されています。
GCSAAで再会したドイツの友人の会社では積極的に自動化を進めているということで、6月にドイツまで視察に行ってきました。
通常タイプのフェアウェイモア
日本でよく見るフェアウェイモアはトロ、ジョンディア、ジャコブセン、バロネスあたりですが、自動化されたものを実用化しているのはどうやら日本のバロネスだけのようですが、先述の通りまだまだ発展途上です。
ドイツのこのコースではターフトロニック(Turftoronic)というオランダの会社のシステムを使ってトロとジョンディアのモアを自動化していました。機械メーカーとは独立に自動化を実現するシステムについては全く聞いたことがなかったので驚きましたが、実際に見てみると完成度はかなり高いです。
この動画ではトロのマシンを使っていますが、ジョンディアでも自動化に関しては全く同じです。この動画を見てもらえれば分かる通り、位置情報サービス(GNSS)と精度を補完するためのRTKを使って1cm程度の誤差の精度を実現していてフェアウェイのエッジも人間が運転するよりもはるかに再現性が高く、刈り込むパターンも美しく浮かび上がっていました。
運転席の屋根のところに前後を監視するLIDARというレーダーがついていて、障害物を検知すると自動で止まります。どれくらい小さいものまで検知するかは未確認ですが、おそらくボール程度のサイズは検知するものと思われます。
このようなレーダーがあるのでホール間の移動も人間が運転するのとほぼ同等のレベルで可能です。ただし、障害物を避けて回り込むことはできないので障害物がある限り停止したままとなり、一定時間停止が続くと管理者へ通知が行く仕組みになっています。なので、人のいない夜間に動かすのはリスクがあるかもしれません。
刈り込みのスピードですが、人間が運転するよりは遅いかもしれないですが、1台で9ホールを刈るのに約6時間と言われていて、毎日9ホールづつ稼働させれば一週間に3回フェアウェイを刈ることが可能で、十分な性能ではないでしょうか。京葉CCでは週に2回が標準頻度ですが、おそらく日本の殆どのコースで週に1回から2回の刈り込み頻度だと思います。
気になる価格ですが、本体価格が45,000ユーロ、マッピングなどの初期設定が5,000ユーロ、ソフトウェアのサブスクリプションが年間4,000ユーロだそうです。モアを買い替えても載せ替えて使うことができるので、かなりお買い得な価格設定のように思います。ちなみに先程紹介したFireFlyは1台3000万円以上するはずで、買い替えるときは丸ごと入れ替えなので、毎回3000万円かかるわけです。ちょっと手が出る金額ではないですね。トロの近年中に自社の自動化モデルを出すと言われてますが、似たような価格になることが予想され普及するか疑問です。
ロボットタイプ
ロボットタイプは一番低い刈高が12mmなのでコーライ芝ならばフェアウェイを刈ることも可能ですが、ローラーがついてないのであまり綺麗ではないし、通常のフェアウェイモアで刈った12mmとは同じ高さではないように見えました。なので、セミラフ〜ラフ用と考えるのが妥当でしょう。
ロボットタイプはハスクバーナとクレスがデファクトスタンダードということで、やまびこのエコーは残念ながらこれらに比べるとかなり性能が劣ると思いました。機械的な部分とソフトウェア的な部分の両方で問題があるように見えました。
クレスがいまのところ一番進んだ機械らしいですが、RTKを使うことで境界のワイヤーも要らないし、コース内にアンテナを設ける必要もないことが優位性です。ハスクバーナはアンテナを設置する必要があるそうです。残念なことにクレスは日本に進出していないので買うことはできません。ハスクバーナも最新の機種は日本にまだ入ってきていません。日本はゴルフコース数がアメリカ、イギリスに次ぐ3番目に多い大きな市場ですが、どういうわけか進出が遅れています。いったいどういう障壁があるんでしょうか。。。
クレスの場合、最大で25,000平米を一日で刈れる性能があり、ハスクバーナの大型のものは50,000平米がカタログ値になります。ラフの面積がどれくらいかはコースによって大きく違うと思うのですが、仮に30万ん平米と多めに見積もったとしてもクレスなら12台、ハスクバーナなら6台あれば毎日刈れる計算です。なによりも人間が刈る場合は週に一回刈れれば良い方で、他の作業が忙しくて間隔が空いてしまうととんでもなく長いラフになってしまったりしますが、ロボットの場合は毎日刈ることが可能なので、ラフのクオリティを一定に保てるのは省力化以上にメリットがあります。
良いことずくめに思えますが、電波で位置をコントロールしているので木の下などは苦手なようです。他にも機械ごとに充電ステーションをコース内に設置しないとならず、通常ゴルフ場というのはコース内には電線が通っていないのでコース内に電線を通すところから始めなくてはならずハードルが高いです。
結論
日本の自動化は思っていた以上に遅れていて、これから一気に進む可能性が高いと思いました。人手不足はヨーロッパも同じですが少子化のスピードが早い日本ではなおさらで、自動化のニーズは非常に高いからです。
費用についてもこれまで聞かされていた噂とは違って現実的な金額だと思います。自動化というと省力化や省コストに注目しがちですが、フェアウェイにしてもラフにしても品質の向上が期待できることが実は最大のメリットだと感じています。
これまでは2台のフェアウェイモアで週に二回刈るのがやっとだったものが、1台で週3回刈れるということはゴルファーは刈りたてのきれいなフェアウェイでプレーできることを意味しますし、芝というのは刈り込み頻度が上がると密度が上がってクオリティが上がるので、その面でもメリットが大きいです。
ラフについては先述の通り、毎日刈れることでプレーヤーは常に一定の長さのラフでプレーできるようになります。これは時間軸でもそうだし、コース内のどの場所も常に同じ刈高を維持できるという意味でもあります。
刈り込み頻度が高いということは刈りカスも短くなるので分解が早くなり病気の原因になりやすいサッチ層が薄くなるメリットもあります。
最新の記事
LOADING...