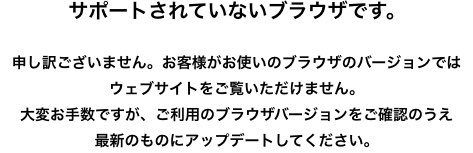ブログ
公開:2017.05.17 10:43 | 更新: 2022.08.25 04:22
R&A サステイナブルセミナー

先日横浜カントリークラブで行われたR&A主催のサステイナブルセミナーに参加してきました。
ゴルフにおけるサステイナビリティとは
サステイナビリティ(持続可能性)とは現在と未来のバランスが取れているということです。現在選択した行動・行為が未来の行動・行為を制限してしまうようなことがないような賢い選択をすることがサステイナブルな社会といえるでしょう。よってそれは環境問題でもあり社会経済問題でもあると考えることができます。現在のゴルフにおけるなんらかの選択や行為が環境を破壊し、将来世代に今ある環境を残すことができなければ、今の世代が享受している環境へ将来世代がアクセスできなくなってしまいますし、社会経済的に見て人々から需要されなくなってしまえばゴルフというスポーツは消えてしまい、将来世代はゴルフをすることができなくなるし、現在ゴルフ産業に従事している人たちが職を失ってしまいます。ですから、自分自身のみならず、自分たちの子供たちの利益を考えて、いま行動を起こすことが求められていると私は考えます。
サステイナビリティを測定する
サステイナビリティは漠然とした理念ではなく測定できなければ効果が明確にならず、よって正しく推進することができません。ISEALという組織は各分野でサステイナビリティを高める運動を行っている組織に認証を与えています。フェアトレード・インターナショナルやレインフォレスト・アライアンスなどもメンバーに名を連ねていますが、ゴルフの分野では今回のセミナーで紹介されたGEO (Golf Environment Organaization)という非営利団体があります。GEOはゴルフ場、ゴルフ場開発者、トーナメントの3分野にそれぞれの認証を与えています。R&Aも積極的に関与しており、全英オープンはGEOの認証を取得しています。ゴルフ場にはOnCourseというオンラインの無料アプリケーションにデータを入力するだけで現在のサステイナビリティが計測され、またOnCourseに登録した各ゴルフ場同士のコミュニケーションの場が与えられていて情報交換ができるようになっています。よくPDCA (Plan Do Check Action) が重要だと言われますが、一番難しいCheck (効果の計測) の部分がこうして外部の信頼できる機関によって提供されていることはゴルフの強みと言え、今回のセミナーに出席して大変心強く思いました。
社会や環境と調和するために
今回のセミナーでサステイナビリティを向上させる具体的なプランとしてコース改造とメンテナンスがテーマとして取り上げられました。
ゴルフ場開発・改造
様々なゴルフ雑誌がゴルフコースのランキングを発表していますが、多くの場合半数以上は戦前のコースがランクインしています。これらのコースは大型の重機のない時代に非常に安価に作られています。何が言いたいかというと、コースの造成費用の多寡とコースの良し悪しは関係ない、ということです。むしろ、おカネをかけて大地を創造したようなコースほどワンパターンで面白みにかけるものになりがちで、サステイナビリティの観点からは環境破壊的でありかつゴルフの楽しみを半減させるような行為と言えるでしょう。
今回のセミナーでもこの点は強調されていましたがより具体的な方法が提示されました。ゴルフ場開発の場合は(1)そもそもゴルフ場に適した土地(地形や土壌の質)を選ぶこと、(2)もとからある地形の変化が生きるルーティング(レイアウト)を取ること、(3)バンカーや池など造成やメンテナンスに費用のかかる要素を必要最小限に留めること、(4)ゴルフ場のスタッフを造成や改造に積極的に関与させること、(5)その土地の気候や土壌に適した芝種を選ぶこと、などが挙げられました。
これらの要素は互いに関係しあっていますが、例えば(2)や(3)と(4)は見逃されがちな点で、コースを造成・改造する業者は費用がかかる方が利益が上がるので放っておくとどんどん地形をいじったり、余計な土壌「改良」剤を入れようとします。しかし、造成後の管理を任されるコース管理責任者やおカネを払う側のゴルフ場のスタッフが積極的に関与していればこういった問題はかなり回避できます(実際、「コンサルタント」の意見のみが取り入れられ、現場の責任者の意見は全く聞き入れてもらえず結局メンテナンスに苦労するという嘆きの声をよーく耳にします)。
メンテナンス
サステイナビリティに関連するメンテナンスに関しては日本のゴルフ場はかなり進んでいると思います。というのも、世界的に問題となっているの温暖化による水不足であり、日本のゴルフ場ではあまり多くの水を必要としないコーライ芝と野芝がゴルフ場のほとんどの面積を占めているからです。これは前節の(5)と関係しますが、気候・土壌に適した芝種を選べば環境への負荷が減ることの好例でしょう。アメリカでも南部地方では水を必要とする洋芝からコーライ芝への転換を検討あるいは実際に転換したゴルフ場は増えているようです。
メンテナンスをそもそも必要としないエリアを増やすことも環境負荷を下げる一つの方策です。これについては日本は遅れていると言えるでしょう。視野に入る全てのエリアがきれいに刈り取られていないといけないと考えているプレーヤーやスタッフがほとんどかと思いますが、これは「オーガスタ・シンドローム」だと思います。マスターズ・トーナメントが行われるオーガスタ・ナショナルは例外であって典型ではないと知るべきでしょう。多くの名コースではラフから少し外れると管理対象外の荒れ地となっていることの方が多いです(ただ、パインバレーのような「カネのかかった荒れ地」もあるのでやっかいです)。
今回会場となった横浜カントリークラブはパネリストとしても来場してたビル・クーア氏によって改造設計されました。改造後の横浜CCではラフの外側では草が伸ばしっぱなしの状態でしたが、むしろそれが景観に良い効果を与えていると思います。とはいえ、まったくボールが行かないわけでもないので論争のタネではあり頭の痛い問題です。

最新の記事
LOADING...