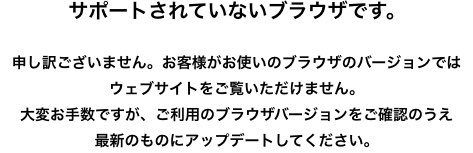ブログ
公開:2014.01.30 10:52 | 更新: 2020.10.24 01:53
ゴルフにおけるフェアネス
ゴルファーはフェアネスを非常に気にする傾向がありますが、僕はこれはかなりどうでもいいことだと思っています。
設計のフェアネス・状態のフェアネス
「フェアである」とは「各プレーヤーが同じ条件でプレーできること」と定義すれば多くの人に同意してもらえるでしょうか。
このように定義した場合、コースの設計はどのプレーヤーにとっても同じなので、常に「設計はフェアである」となります。しかし、どのコースにも有利不利はあり、例えばオーガスタは昔からドローヒッター有利とされています。それではこれをもってオーガスタはフェアではない、フェードヒッターにも同程度有利になるように改造すべきだ、となるでしょうか。
すべてのコースはロングヒッターに有利にできています。ロングヒッターはいつでも短いクラブを使うことでショートヒッターになれるからです。だからこそゴルファーは飛距離アップに血道を上げるわけです。では距離の長いコースはアンフェアなのでしょうか。
今度は林間コースでのドッグレッグを考えてみましょう。ロングヒッターはグリーンを狙えるところまで飛ばせるが、ショートヒッターはそこまで飛ばず、林が邪魔で3打目勝負を余儀なくされるようなホールです。これはフェアでしょうか、アンフェアでしょうか。
ときどきバンカーの先に木が植えられているようなホールを見かけます。グリーンを狙う方向にボールを打つことが不可能なケースです。ダブルハザード(和製英語かと思いますが)とも呼ばれますが、これをアンフェアという人がいますが、どうでしょうか。上述の定義に照らせばアンフェアではないですよね。
このように考えると、コース設計由来のフェア・アンフェア問題は存在しないといえると僕は思います。単につまらないコースという烙印を押されるだけでしょう(よほどのマゾではない限り)。
では、コースの状態についてはどうでしょうか。マッチプレーであればほぼ同じ時刻にプレーするのであまり状態の変化はないのでフェアな状態を保てていると言えると思いますが、ストロークプレーの場合、スタート時間によって大きな差が出ることが普通です。
午前中は風が吹いていたのに午後は吹かなかったり、午後になったら雨が降り始めたりします。また、芝は一日のうちに伸びてくるので芝種によっては午後になると顕著に転がりが悪くなったりもします。最終組は多くのプレーヤーに踏まれ、凸凹になったグリーンでプレーします。しかし、これらは人智の及ばぬ自然の摂理の領域で、これをアンフェアだとするのは理不尽だと思います。
バンカーの砂質についても「フェアではない」とよく苦情が出ます。砂が柔らかければ目玉になりやすいと苦情が出ますし、硬ければクラブが跳ねると苦情が出ますが、結局は自分が打ちやすい状態を求めているだけなのだと思います。
ようするに何がいいたいかというと、フェアネスの概念を持ちだして自分のプレーを正当化するのは筋が悪い、ということです。そこが裸地であろうと、舗装された道路であろうと何であろうとあるがままにプレーするのがゴルフの基本です。ルールがそのような状況からの救済を許しているのは単に安全性の確保のためとゴルフのゲームとしての面白さを損ねないためだと思います。フェアネスとは何の関係もないと思います。
フェアネスではなく面白さを基準に
僕は上記すべてのケースにおいてフェアネスではなく、それぞれのプレーヤーが面白いと感じるかどうかを基準に考えればスッキリすると思っています。例えば、先ほど挙げた林間コースのドッグレッグの例を使うと、ドッグレッグを林ではなくバンカー群で実現すれば、ショートヒッターにもバンカーを迂回するルートとバンカー越えを狙うリスクを取ったルートという選択肢が実現し、面白さが増すといえるのではないでしょうか。このような発想の転換はフェアネスに立脚していてはできないと思います。ショートヒッターがロングヒッターに対して不利なことは変わっていないからです。
どうやら多くのゴルファーは「ゴルフコースはこうあるべき」というあるべき姿のイメージを持っているようです。しかし、僭越ながら僕は全く逆の考え方を持っていて「ゴルフコースはこうあるべきという姿は存在しない」と思っています。
マスターズは全世界的に見ても唯一毎年同じコースで開催されるメジャートーナメントだと思いますが、その会場であるオーガスタの美しい映像は日本人のみならず世界中のゴルファーを魅了しています。しかし、オーガスタはひとつの頂点ではあるものの、他にもまったく異なる方向性の頂点に立つコースが数多くあります。単にランキングという意味で言えば、はるかに格上と言えるパインバレーはオーガスタとは全く性格の異なるコースですし、セントアンドリュースもそれら二者とも違います。むしろ違うからこそ面白いわけです。
しつこいですが、バンカーの砂質についてもう一度考えてみましょう。日本ではバンカー用の砂はバンカー用の砂として流通しています。この砂を使うと目玉になりにくいし、本当に気持ちよくバンカーから球が出ます。スピンが掛かって止まります。プレーヤーの気持ちを考えたおもてなしの心を持ったバンカーになります。おそらくアメリカでも似たような状況だと思います。どこにいっても真っ白い砂で非常に打ちやすいです。この状況をトム・ファジオは「オーガスタシンドローム」と呼んでいます。オーガスタこそがあるべき姿であるとの誤解がアメリカでも蔓延していることを揶揄した表現です。
本来のゴルフは自然との戦いだと思います。リンクス(スコットランドの言葉で「砂丘」の意味)ではその名の通り砂丘の上にコースがあるので、穴を掘れば砂が出てきてバンカーになります。「バンカー用の砂」なんてものは存在しません。なので、その土地によってバンカーの砂質は異なります。セントアンドリュースのバンカーの砂などはサラッサラの極端に難しい砂質で、日本で使ったら苦情が止まらないと思いますが、セントアンドリュースでバンカー砂の文句を言っている人がいたら相当滑稽に見えますよね。
こんなこともありました。ある日本人の設計者の方が京葉を訪れて「ここはフェアウェイが少し張っていて、フェアウェイにティーショットが落ちてもヘタするとラフにまで散らばってしまうし、どこへ行くかわからないからフェアではない」と指摘されました。同時に「フェアウェイを少し削ってラフを盛り上げるべきだ、そうすれば、ボールはフェアウェイに集まってくる」とも。なるほど日本には凹型になったフェアウェイが多いのはこの考え方が設計者の間で一般的だからなんだなと納得しました。ここでもおもてなしの心が発揮されていて、なるほどと妙に感心した記憶があります。たしかに良いスコアが出ると面白いのですが、みんながみんな、このタイプの「面白さ」を求めているとしたら、なんだかガッカリですね。
最新の記事
LOADING...