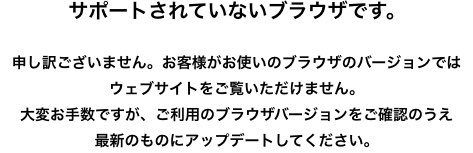ブログ
公開:2011.02.17 11:01 | 更新: 2020.10.24 02:03
日本で「スループレー」は何故採用されない?
18ホールを長い休憩を挟まずにプレーすることを日本では「スループレー」と呼んでいて、「スループレー」することは日本では特殊なこととされる。この点についてゴルファーの希望を聞いてみると、殆どの人が「スループレー」の方が良い、という。多くのゴルファーが望んでいるのに日本ではそれが実現されない、もしくは廃れてしまったのは何故なのだろう?長期的な利益を最大化するという目的はゴルフクラブの形態を問わず同じはずで、ゴルファーの満足度を高める方法が採用されないのは不思議だ。今回はこのことについて考えてみたい。
2つの基本方式
ワンウェイ方式
「スループレー」には基本的に2つのやり方がある。まず全ての組を1番ホールからスタートさせるワンウェイ方式がある。この方式の場合、日が昇ってからスタートを開始し、18ホールのプレー時間分を日没時刻から引いた時間が最終スタートになる。例えば6時に日が出て、18時に日が沈み、プレーに4時間かかる場合は単純にいえば6時から14時までスタートできることになる。10分間隔でスタートするとすると、8時間あるので49組スタートできる計算だ。セントアンドリュースなど古いコースは10番ホールが遠いためワンウェイ方式を取らざるをえないことが多い。下にワンウェイ方式を図にした。
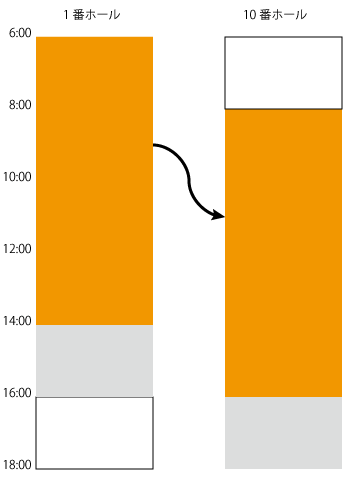
オレンジで塗られた部分が、1番ホールからスタートする組の時間を表していて、右側はそれらの組が10番ホールに来る時間を示している。グレーの部分はスタートする組はないものの、フロントナイン(アウトコース)またはバックナイン(インコース)をプレーしている組があることを示していて、白地は誰もプレーしていないことを示している。これを見ると、白地の部分はそれぞれの9ホールで2時間ずつあることがわかる。この面積が大きいほど、ゴルフコースが有効に活用されていないことになる。
ツーウェイ方式
さて、もう一つの方法は1番ホールと10番ホールから同時にスタートするツーウェイ方式であるが、この場合には午前組と午後組にスタート時間が分かれることになる。図で示すと次のようになる。
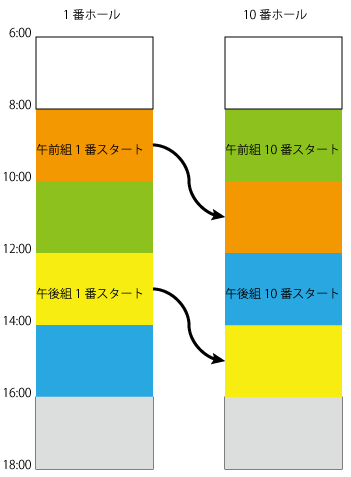
8時を午前組のトップスタートとして、10時が最終組になる。10時になると1番ホールには10番ホールから最初にスタートした組がやってくるので、10時から12時までは新たにスタートできる組はない。このため、午前組と午後組とに分かれるのである。この場合には白地の面積はそれぞれ2時間分で同じである。
変則ツーウェイ方式
最後に、現在関東地方で主流の休憩を挟んだ、変則ツーウェイ方式を図で示してみる。
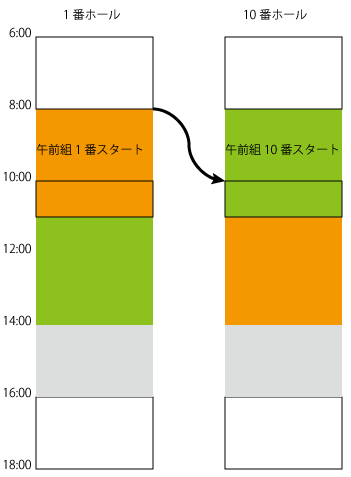
8時にスタートした組が10時に9ホールを終えて1時間休憩するとその間午前中のスタート時間を増やすことができる。しかし、全体では白地の面積が各4時間と倍になっていて無駄が生じていることがわかる。
日照時間の影響
ここまでは日照時間が12時間、18ホールのプレー時間が4時間という想定で考えてきたが、日照時間は季節や緯度によっても変わるし、現在のプレー時間を4時間と想定することは現実的はない。想定するプレー時間が4時間よりも長くなる、ということは日照時間が短くなるということと同じなので、日照時間の変化についてのみ考えることにする。(日照が8時から16時までと仮定する)
ワンウェイ方式では単純にスタート時間が短くなるだけで、ロス(白地の面積)は変わらない。
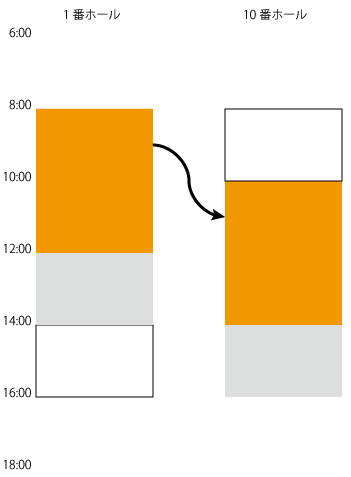
ツーウェイ方式では4時間日照時間が短くなると午後組が完全に消滅してしまう。日照時間の減少が想定プレー時間よりも短ければ、その分だけ午後組の枠を確保することができる。
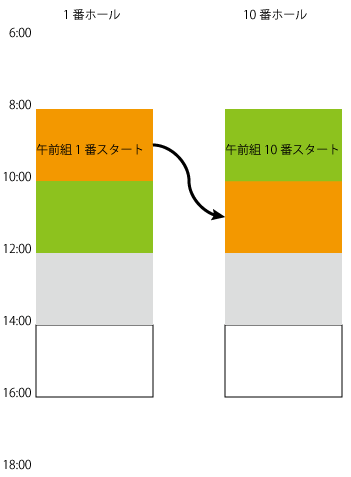
これらに対して、途中休憩をとる変則ツーウェイ方式では、プレーヤーに休憩をとらせるという(プレーヤーにとっての)コストを代償として利用効率のロスを減少させることができる。
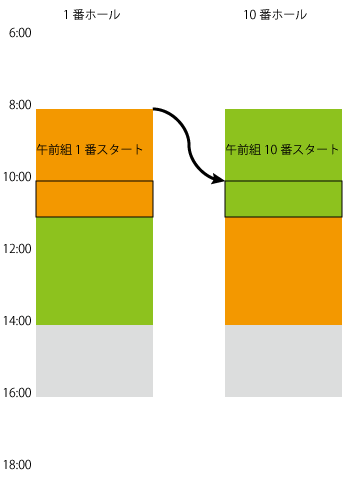
ここまでのまとめ
日本の時刻の基準は兵庫県にあり、それより東に位置する関東地方では時刻に対しての日没が早いので、生活リズムを基準とした日照時間が短い。このため1年のかなりの期間が変則ツーウェイ方式がゴルフコースにとっては効率的であり、その効率化の結果として価格を(そうでない場合に比べて)低く抑えることができるため、供給サイドであるゴルフコースにとってもプレーヤーにとってもメリットのある方法であったといえる。
さらに、関東地方のゴルフコースへの交通事情や1日の有効利用という観点から遅い時間のスタートに対する需要の低さも要因の一つとしてあげられるだろう。どれだけスタートの「枠」があったとしても、そこでプレーするプレーヤーがいなければその枠はないも同じだからである。
これらの考察から、プレーできる時期の日照時間が非常に長いスコットランドでワンウェイ方式が多く(古いコースが多いので必然的にワンウェイにならざるをえない場合も多いが)、アメリカではツーウェイが普及し、日本では変則ツーウェイが普及したのには日照時間(プレー時間も含めて)とアクセスの違いが大きな影響を与えたのではないかと推察される。
それでも「スループレー」を普及するために
日本、とくに関東地方では合理性が乏しいゆえに普及しなかった「スループレー」であるが、それを「スループレーは世界の標準であるのに、それをさせないゴルフコースに問題がある」というのは単なる精神論に過ぎないので、ここでは合理的な解決方法を考えていきたい。
まず考えられる当然の方法は、日照時間の長い時期にはワンウェイ方式なりツーウェイ方式を採用し、日照時間の短い時期には変則ツーウェイ方式を採用することである。日照時間が長いほどワンウェイ方式が合理的になるが、日本はワンウェイ方式が合理的になるほど日照時間が長い日はあまりないので、ツーウェイ方式が現実的な回答である。
実際にツーウェイ方式を採用するに当たっての問題点は、これまで変則ツーウェイ方式で午前中にプレーを開始する方法に慣れたプレーヤーが多い中、午後のスループレーに需要があまりない可能性があることである。通常プレーヤーが「スループレーのほうが良い」という場合には午前組でのプレーを想定していて、午後のプレーが普及しないとスループレーが成立しないことまでは考えていない。
これを解決するひとつの方法は、人気の低い午後スタートの料金を引き下げてインセンティブを与えることである。料金そのものは午後組への需要の強さによって決まるが、ツーウェイ方式を採用するかどうかは変則ツーウェイとの比較によって決まる。午後組への需要があまりに弱くて設定料金が低くなりすぎればスループレーは維持できなくなるであろう。
最新の記事
LOADING...