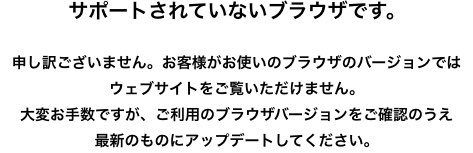ブログ
公開:2010.04.22 11:12 | 更新: 2020.10.24 02:12
世に用あり、餘に用なし
…自分には用がないのだらう。それを世に用なしと思ふのだ。よく考へてみると、いろいろなものゝ實用、實用といふ場合は、大槪これです。餘に用なしなんです。餘に用なしといつても、自分ではどんな恩惠を被つてゐるか知らない。間接に恩惠を被つてゐるのだが、それを自分が認識しないで、餘に用なしと思つてゐるのだ。だから實際は、餘に用なしでもないのだ。
—高木貞治「數學の實用性」
「生兵法は怪我の元」、「論語読みの論語知らず」、「論より証拠」、「机上の空論」など「理論」に対する反感は非常に根強いものがあるように思う。でも、人間誰しもが「理論」に基づいて判断しているんだよね。その「理論」が個人的な経験から導かれたものであるか、別の人達の間で積み上げられてきた知的営為の蓄積なのか、の違いがあるだけなんだ。
でも、ここに埋め難い溝が存在してる。自分が経験したことっていうのは非常に強烈なるインパクトを記憶に残すから、これこそが絶対であると錯覚しがちである一方、他人の論じるもので自分の経験外のものや、経験に反するものについてはどこか非現実感が漂うわけで、主観的評価が低くなってしまうことにもうなづける。
うなずけるとは言ったものの、このような「感覚」が一般的な社会通念となって反知性主義が蔓延すれば、社会の進歩が停滞することもまたかなり明らかだと思う。だから、知的営為の個人的な蓄積と社会的な蓄積とを較べた場合、社会的蓄積を優先させることが望ましい、って考えるのが妥当な線じゃなかろうか。
「こんなものは役に立たない」という言葉を口にしたくなったとき、それが「自分が役に立てられない」だけなのか、それとも「役に立てられる人が一人もいない」ということなのかをまず考えてみたらいいんじゃない?という話でした。
最新の記事
LOADING...